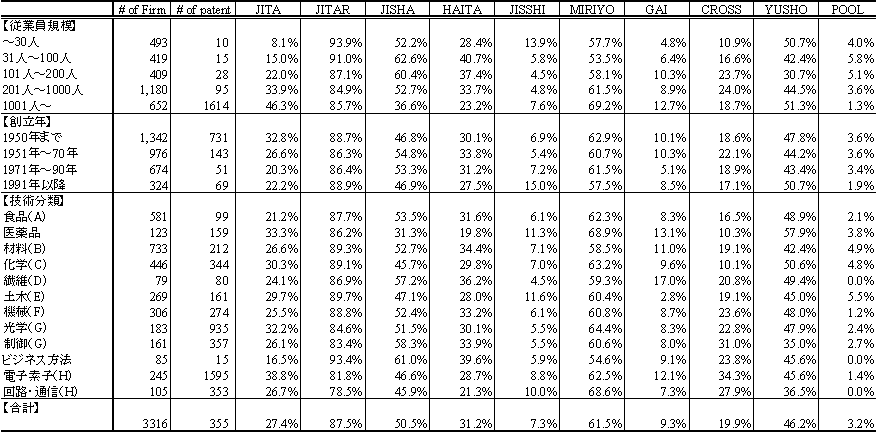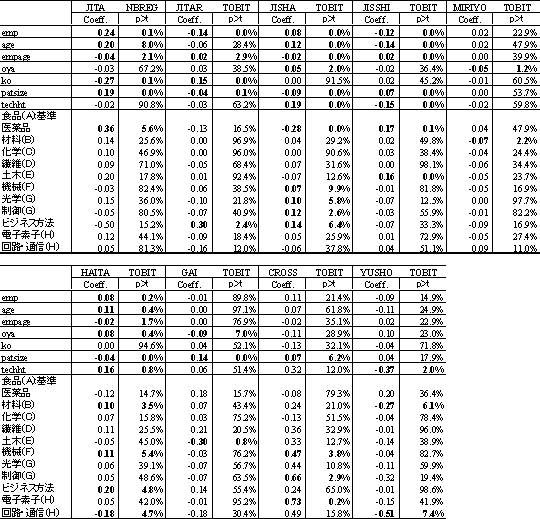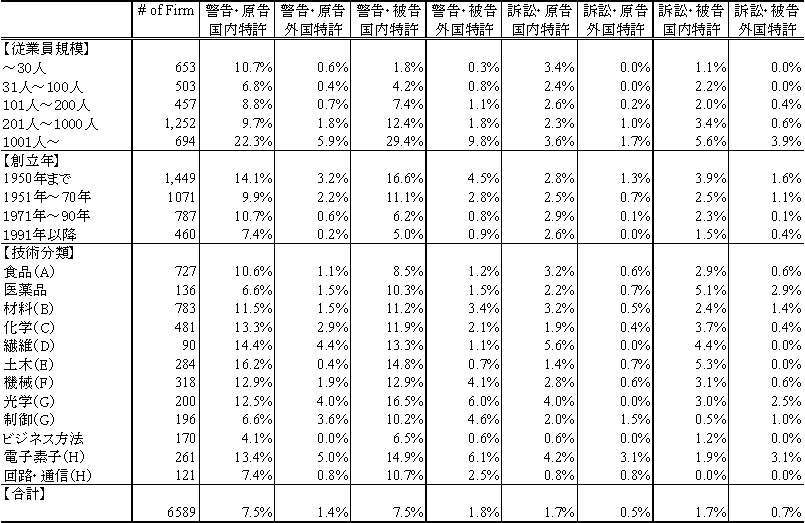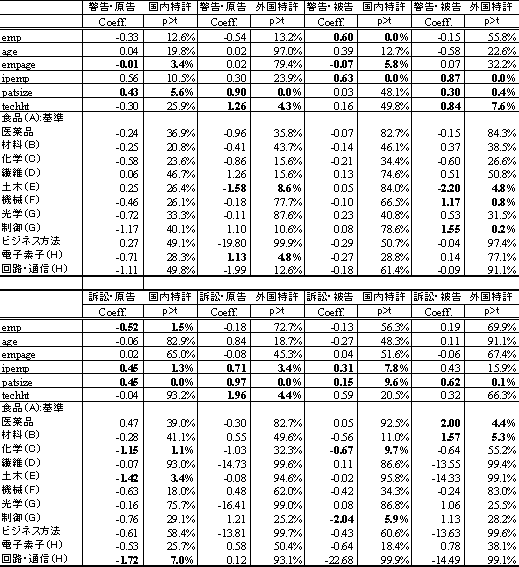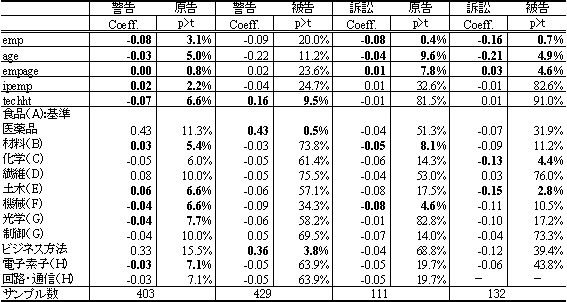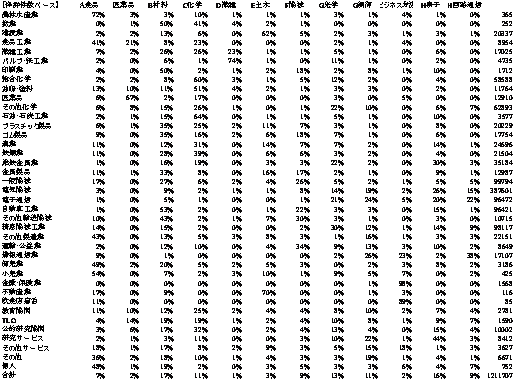�������x�ƌ����J���^������Ƃ̃C�m�x�[�V����
������w��[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[��
�o�ώY�ƌ������@�����@��V
(�v��)
�������x�́A���Y��̔��Ɋւ���o�c���\�[�X�ɖR�����A�����J���ɂ��̊����̏d�_��u���Ă��錤���J���^������Ƃ��A�Z�p�̐�L�\��(appropriability)���m�ۂ����ŏd�v�Ȑ��x�ł���B���������̈���ŁA�������̃��C�Z���V���O�����������Ɋւ��镴�����������ꍇ�A������Ƃ͑��ΓI�ɕs���ȗ���ɂ�����Ă���Ƃ����l����������B�����ł́A�������ɂ��m�I���Y�������Ԓ����̓����̎��{�Ɠ��������Ɋւ���f�[�^��p���āA�������x�ƌ����J���^������Ƃ̃C�m�x�[�V�����Ɋւ�����ؕ��͂��s�����B
�����̎��ЕۗL�����̎��{�ɂ��ẮA��ƋK�͂���������ƔN��Ⴂ��Ƃ́A���Ў��{�������Ⴍ�A���Ў��{�������������Ƃ����������B�t�ɁA���Ђ̓����̎��Ђւ̎��{�ɂ��ẮA���ƂƔ�ׂĊ����ɍs���Ă��Ȃ��Ƃ������ʂɂȂ����B�o�c�����̖R����������Ƃ��A�����J���̐��ʂ����O�Ŏ��{���Ċ�Ɨ��v�ɂȂ��Ă������Ƃ�����ł��邽�߁A���Ђւ̃��C�Z���V���O�����������Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�������x�͂��̂悤�ȊO���Z�p�}�[�P�b�g���m��������̂Ƃ��āA���Ɍo�c�����ɖR����������ƂɂƂ��Ă͏d�v�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�܂��A���������Ɋւ��镪�͂̌��ʁA��ƋK�͂��������A��ƔN��̎Ⴂ��ƂقǕ����m���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������B���������{�Ɋւ��镪�͌��ʂɌ����悤�ɁA������Ƃ͓����̑��Ђւ̃����Z���V���O��ϋɓI�ɍs���Ă����K�v������B�]���āA���������Ɋ������܂��m���͎����ƍ��܂�Ƃ������Ƃ��l������B����̕��͌��ʂł́A�����̎��ɂ��ẴR���g���[�����ł��Ȃ�������������Ƃ����C�Z���X���ɂ����Ďア����ɂ���\�����������Ă���B
�P�D
���ӎ�
�@���{�̃C�m�x�[�V�����V�X�e���́A���Ƃ𒆐S�Ƃ������O��`�̌X�����������Ƃ������ł���ƌ����Ă��邪�A���Ƃɂ����Ă������J���Ɋւ���O���A�g��������������ɂ���B�܂��A���̂Ƃ���Y�w�A�g�̓����������J���^�̒�����ƂɍL�܂����A�l�b�g���[�N�^�̃V�X�e���ւ̕ϊv�ւ̒����������Ă���(�����2003)�B����IT��o�C�I�e�N�m���W�[�̂悤�ȋZ�p�v�V���}���ɐi�ރn�C�e�N����ɂ����ẮA�Z�p�s���ʂ��������J���Ɋւ���O���A�g��L���Ɋ��p���邱�Ƃ̏d�v�������܂��Ă���iArora et al., 2001�j�B�l�b�g���[�N�^�̃C�m�x�[�V�����V�X�e���ɂ����āA�hagent of change�h�Ƃ��Ă̌����J���^������Ƃ̉ʂ��������͑傫��(Audretsch, 1999)�B�����ł͒�����Ɓi���Ɍ����J���^�x���`���[��Ɓj�̃C�m�x�[�V�����������������邽�߂̓������x�̂�����ɂ��Č������邱�ƂƂ���B
�@�m�I���Y���x�́A�O���Z�p�s��̌`���ɂ͕s���̂��̂ł���A�����J�����琻���A�}�[�P�e�B���O�܂ł̃o�����[�`�F�[�������Ѓ��\�[�X�ōs�����Ƃ�����Ȓ�����ƂɂƂ��ĈӋ`�͑傫��(Hall and Ziedonis, 2001)�B���������̈���Ŏ��ЂɃp�e���g�|�[�g�t�H���I���������N���X���C�Z���X��L���Ɏg���Ȃ�������Ƃ̓����Z���X���ɂ����ĕs���ȗ���ɗ�������Ă���ƍl������B�܂����������ɑ���Г����\�[�X�����������Ƃ���A���������ɂ����Ă����ΓI�ɕs���ȗ���ɂ���ƌ����Ă���(Lanjouw and Schankerman, 2001, 2003)�B
�@�����̒m�I���Y���x��������Ƃ̃C�m�x�[�V�����ɗ^����e���Ɋւ���c�_�͎�ɕč��ɂ�������ؕ��͂��x�[�X�Ƃ������̂ł��邪�A�����ł͒m�I���Y�������Ԓ����i�������j�̌[�f�[�^��p���ē��{�ɂ����錻��ɂ��ĕ��͂��邱�ƂƂ���B�m�I���Y�������Ԓ����i�ȉ��A�u�m�������v�ƌĂԁj�ł́A��Ƃɂ���������ۗ̕L�A���p�̑��A�����Ɋւ��镴���̏Ɋւ��钲�����s���Ă���B�ȉ��A�܂������ۗ̕L�Ƃ��̎��{�ɂ��Ċ�ƋK�́A�n�ƔN�A�Z�p����Ɍ��邱�ƂƂ���B���ɓ����ɂ������x����i�ׂɊւ���f�[�^��p���āA���������ɂ����钆����Ƃ̌��͂Ɋւ��镪�͂��s���B�Ō�ɂ����̕��͌��ʂ�ʂ��ē������x�ƃn�C�e�N�x���`���[�̃C�m�x�[�V�����ɑ���C���v���P�[�V�������q�ׂ�ƂƂ��ɁA�f�[�^���p�҂̗��ꂩ�獡��̒m�������ɂ�����ɂ��Ă��G�ꂽ���B
�Q�D
�����ۗ̕L�Ɨ��p�Ɋւ����ƋK�͊Ԋi��
�m�������ɂ����Ă͊�Ƃ��Ƃ̒m�I���L���ۗ̕L�Ɨ��p�̎��Ԃɂ��ďڍׂȒ������s���Ă���B�������x�ƒ�����Ƃ̃C�m�x�[�V�����Ɋւ��镪�͂��s����ŁA�����̃��C�Z���X�̌`�ԁi�L���A�N���X���C�Z���X���̓p�e���g�v�[���j�⑼�Ќ����̎��{�����Ɋւ�����͋M�d�ł���B�����ł͂܂��A��ƋK�͕ʁA�n�ƔN�ʁA�Z�p����ʂɂ݂������ۗL�A���p�̏ɂ��Ă݂邱�ƂƂ���B�Ȃ��A��Ƃ̋Z�p����ʕ��ނɂ��ẮA�o��i�\��j�����̋Z�p����ʕ��z�Ɋւ���f�[�^��p�����B�ڍׂɂ��ẮA�ʓY�̕t�����Q�Ƃ��ꂽ���B�܂��A�f�[�^�̃T���v���Ƃ��ẮA�@�t���̕��@�ɂ���ċZ�p��������߂邱�Ƃ��ł��A�A���ЂŕۗL���Ă�����������݂��A���B�]�ƈ����Ƒn�ƔN�ɉ�����3316��Ƃł���B
���ʂɂ��Ă͕\�P�̂Ƃ���ł���B�������p�̏ɂ��ẮA�������ڂ�p���Ĉȉ��̂Ƃ���w�W���������̂�p���Ă���B
�E
JITA�F���Ќ����̎��Ў��{���s���Ă��邩�ۂ��i�_�~�[�ϐ��j
�E
JITAR�F�����������p�����^�i�����������p�����{���Ќ������{�����j
�@�@�@�@�@�i���Г������p���������Дr���I���{�E���Ќ������{���Ђւ̎��{���Ќ������j
�E
JISHA�F���Ў��{�����^�������L����
�E
HAITA�F���ЂŔr���I�Ɏ��{���Ă��鎩�Ќ������^�������L����
�E
JISSHI�F���Ђ̑��Ђւ̎��{�����^�������L����
�E
MIRIYO�F�����{�����̊����i�P�|HAITA�|JISSHI�j
�E
GAI�F�O����Ƃւ̎��{�����^���Ђւ̎��{������
�E
CROSS�F�N���X���C�Z���X�ɂ�鑼�Ђւ̎��{�����^���Ђւ̎��{������
�E
YUSHO�F�L���ő��Ђ֎��{���Ă��錏���^���Ђւ̎��{������
�E
POOL�F�p�e���g�v�[���ɂ�鑼�Ђւ̎��{�����^���Ђւ̎��{������
(�\�P)
�܂��A��ƋK�͂��傫���Ȃ�قǎ��Г����𑼎Ђ֎��{���銄���iJITA�j�������Ȃ�A���ЂŎ��{���Ă�������̂������Г����̊����iJITAR�j���Ⴍ�Ȃ�B����Ŋ�ƔN��i�n���N�j�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�͂����肵���X���������Ȃ��B���ЂŎ��{���Ă�������̊����iJISHA�j�Ǝ��ЂŔr���I�Ɏ��{���Ă�������̊����iHAITA�j�ɂ��ẮA30�l�ȉ��̊�Ƃ������Ċ�ƋK�͂��傫���Ȃ�قlj�����X���ɂ���B�t�ɖ����{�����iMIRIYO�j�̊����͋K�͂��傫���Ȃ�A��ДN������Ȃ�قǑ傫���Ȃ��Ă���B���̂悤�ɁA��ƋK�͂��傫���Ȃ�Ǝ��Г����̎��{����������Ɠ����ɑ��Ќ����𗘗p���銄���������Ȃ�Ƃ������X����������B
���Ђւ̌����̎��{�`�Ԃɂ��ẮA��ƋK�͂��傫���Ȃ�ƊO���ւ̎��{���������iGAI�j��N���X���C�Z���X�������iCROSS�j�����Ȃ邪�A�L���ɂ�郉�C�Z���X�̊����iYUSHO�j��p�e���g�v�[����p���銄���iPOOL�j�ɂ��Ă͍ۗ������X���������Ȃ��B�܂��A��ƔN��ɂ��ẮA��ƋK�͂Ɣ�ׂđS�̓I�ɖ��m�͌X���������Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B
�܂��A�Z�p����Ƃ̊W�ɂ��ē����I�ȓ_�����グ��ƁA�u�d�q�f�q�v�A�u���i�v�A�u���w�v�ɂ����đ��Г�������葽�����p����Ă���B�����̋Z�p����ɂ��Ă͎��Г����̑��Ђւ̎��{�����������Ȃ��Ă���A�����J���ɂ����ē����̃����Z���V���O�헪����r�I�d�v�ł���Ƃ������Ƃ�������B�������A�u���i�v����ɂ��Ă͑��Ђւ̎��{�������̂����N���X���C�Z���X���g���������Ⴍ�A�L���Ń��C�Z���V���O���s�������������Ȃ��Ă���B���̈���Łu�d�q�f�q�v�����u����v����̓N���X���C�Z���V���O�𑽂��p���Ă������ŗL���̊��������Ȃ��Ȃ��Ă���A�Ή���Ȃ��N���X���C�Z���V���O��p����P�[�X���������Ƃ������Ă���B
���̂悤�Ȋ�ƋK�́A��ƔN��y�ыZ�p����ɂ��������p�̏����ڍׂɌ��邽�߂ɁA�������p�Ɋւ���e�w���������ϐ��Ƃ��āA�ȉ��̕ϐ�������ϐ��Ƃ����A���͂��s�����B�Ȃ���A���̓��f���́AJITA�ɂ��Ă�negative binominal���f���ł���ȊO�̕ϐ��ɂ��Ă͗��[�ؒf�^Tobit���f����p�����B
�E
EMP�F��ƋK�́i�]�ƈ����̎��R�ΐ��j
�E
AGE�F��ƔN��i�N�̎��R�ΐ��j
�E
EMPAGE�FEMP��AGE�̌�����
�E
OYA�F�e��Ƃ̗L���Ɋւ���_�~�[�ϐ�
�E
KO�F�q��Ђ̗L���Ɋւ���_�~�[�ϐ�
�E
PATSIZE�F�p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���i���L�����̎��R�ΐ��j
�E
TECHHT�F��Ƃ̏o������Z�p���ށi8���ށj�Ɋւ���n�[�t�B���_�[���w��
�E
��Ƃ̋Z�p���ނɊւ���_�~�[�ϐ��F�u�H�i�v���
���ʂɂ��Ă͕\�Q�̂Ƃ���ł���B
(�\�Q)
�܂��A��ƋK�͋y�ъ�ƔN��Ƃ̊W�ł��邪�A�K�͂��傫���Ȃ�قǁA�N������Ȃ�قǑ��Ђ���̎��{�����A���Г����̗��p�������Ⴍ�Ȃ�Ƃ����W���m�F�ł����B�܂����ЕۗL�����̎��{�Ɋւ��ẮA�K�͂̑傫����Ƃł͎��Ў��{���������Ȃ�A��������Ƃł͑��Ў��{���������Ȃ�Ƃ������ʂɂ��Ă��\�P�Ɠ��l�̌��ʂƂȂ����B�Z�p����₻�̑��̗v�����R���g���[���������Ƃɂ���Ċ�ƔN��Ƃ̊W���\�Q�ł͂�薾�m�ɂȂ��Ă���B�܂��A�����̕��͌��ʂɂ�����empage�i��ƋK�͂Ɗ�ƔN��̌������j�̌W���͊�ƋK�́A��ƔN��ꂼ��̌W���̕����Ƌt�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɗ��ӂ���K�v������B�Ⴆ��JISSHI�Ɋւ��镪�͌��ʂł́A��ƋK�͂��傫���Ȃ�قǑ��Ў��{�����������Ȃ��Ă��邪�A���̉e���͊�ƔN��̎Ⴂ��Ƃł��傫�����Ƃ�\���Ă���B�i��ƋK�͂ɂ�鑼�Ў��{�����̉e�����|0.12�{0.02AGE�A�܂�AGE�̑傫����Ƃɂ����Ă̓}�C�i�X�̐�Βl���������Ȃ�j�܂��A��ƔN��̉e���ɂ��Č���ƁA��ƋK�͂̏�������Ƃł��傫�ȉe�������邱�Ƃ������Ă���B�i��ƔN��ɂ�鑼�Ў��{�����̉e�����|0.14�{0.02EMP�j�܂�A��Ƃ̐����p�^�[�����l����ƋK�͂ƔN��͒ʏ퐳�̑��֊W������ƍl�����邪�A������JITA�AJITAR�AJISHA�AJISSI�Ȃǂ̗^����e���ɂ��Ă͔�r�I�Ⴍ�A�K�͂̏�������Ƃɂ��Ă͓��Ă͂܂邪�A������x�̋K�͂ɒB����Ƃ��̉e���͏������Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł���B
PATSIZE�͊�Ƃ��̂��̂̑傫���Ƃ������A��Ƃɂ�����p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���������Ă���BJITA�y��JITAR�ɂ��Ă͊�ƋK�́iEMP�j�Ɠ������ƂȂ��Ă��邪�AJISHA�AJISSHI�y��HAITA�ɂ��Ă͋t�̕����ƂȂ��Ă���B�Ⴆ�Ί�ƋK�͂��傫���Ȃ�قǎ��Ў��{�����iJISHA�j���������A�p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫���Ȃ�Ǝ��Ў��{������������B���Ȃ݂ɑ��Ў��{�����iJISSHI�j�ɂ��Ă͂��̋t�̌��ʂƂȂ��Ă���B��ƋK�͂���������ƔN��Ⴂ��Ƃɂ����ẮA���Ђ̃��\�[�X�Ő����A�̔��܂Ńo�����[�`�F�[�����ׂĂɑΉ����邱�Ƃ͍���ł��邱�Ƃ���A�����J�����ʂ𑼎ЂɎ��{����X�������܂�ƍl������B���̈���Ńp�e���g�|�[�g�t�H���I����������Ƃ͑��ЂɎ��{��������̐��������Ă���A���Ђւ̎��{�����������邱�Ƃ��l������B�܂��ATECHHT�̉e���ɂ��Č���ƁA�p�e���g�|�[�g�t�H���I�����蕪��̃t�H�[�J�X����Ă���iTECHHT���傫���j��Ƃɂ����ẮA���Ђւ̎��{�������������Ȃ�A���Ђł̎��{�����������Ȃ��Ă���[1]�B��Ƃ������J�����s���ۂɁA���Њ��p����Ƀt�H�[�J�X���邩���Ђւ̃��C�Z���V���O���ɂ��L�����̂Ƃ��邩�Ƃ�������Ɛ헪�̈Ⴂ������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
���Ђւ̃��C�Z���V���O���s���ۂ̂��̌`�Ԃɂ��ẮAEMP�Ƃ�������Ƃ̈�ʓI�ȋK�͂ɂ͉e�����Ă��Ȃ��B���̈���Ńp�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���͑��Ђւ̎��{�������ɐ�߂�N���X�����Z���V���O�̊����Ɛ��̊W��������B���̊W�́A�p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫���ƃN���X���C�Z���X�̑���ɂ����ĕK�v�ȓ������܂܂��m���������Ȃ邱�Ƃɂ��ƍl������B�����J���̃t�H�[�J�X�iTECHHT�j�ɂ��ẮA�L���ɂ����{�����ƕ��̊W��������B���̈���ŃN���X���C�Z���V���O�̌W���́A���v�I�ɗL�ӂł͂Ȃ����̂̐��ł���BTECHHT�����߂邽�߂ɗp�����Z�p���ނ�12����Ƒe�����̂ł��邱�Ƃ���A�P�̕���ɏW������قǓ��蕪��ɂ�����p�e���g���x�������Ȃ�A�N���X���C�Z���V���O���s���₷���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�t�ɑ��Ђւ̃��C�Z���X���ɂ��p���헪���Ƃ��Ă���ꍇ�́A�L���Ń����Z���V���O���s���X�������������ƍl������B�������A���̓_�ɂ��ẮA���ڍׂ̓f�[�^��p���čX�Ȃ錟���s�����Ƃ��K�v�ł���B
�@�Ō�̋Z�p����Ɠ����̎��{���@�̊W�ł��邪�A�u���i�v����ɂ��ẮA���Ђ̓�������葽�����p����ƂƂ��ɁA���Г����̃��C�Z���X�����������ɍs���Ă���Ƃ����X���́A��ƋK�͓����R���g���[��������ł������Ă���B���̈���Ŏ��Ђɂ�����������{�����������̂́A�u�r�W�l�X���@�v�A�u����v�A�u���w�v�A�u�@�B�v�Ȃǂł���B�܂��A�u�d�C�f�q�v�ɂ��ẮA���Њ������ɂ��ē��i�̓����͌����Ȃ��������A�N���X���C�Z���X�ɂ�鑼�Ђ̊����������Ƃ������ʂɂȂ��Ă���B
�R�D
���������̎��ԂƊ�ƋK�͊Ԋi��
�@�m�������ɂ����ẮA�m�I���Y���Ɋւ���x����i�ׂ̌����Ɋւ��钲�����s���Ă���B�����ł͓����Ɋւ��镴���̎��Ԃɂ��Ċ�ƋK�͊Ԋi���ɏœ_��u���Č��邱�ƂƂ���B�Ȃ��A�m�������ł͒��߂̉�v�N�ɂ�����m�I���Y���̕����ɂ��āA�@�x�������Ƒi�����A�A�����������O���������A�B������Ƃ��C�O��Ƃ��i�C�O��Ƃɂ��Ă͕č��A���B�A�A�W�A�y�т��̑��j�A�C�u�i����v���i�����j���u�i������v���i�퍐�j���̃}�g���b�N�X�Œ������s���Ă���A�����������ł�2�~2�~5�~2��40�̒������ڂƂȂ��Ă���B����14�N�����ł��ꂼ��̍��ڂɂ����ĊY������Ƃ����T���v�����͈ȉ��̂Ƃ���ł���B[2]
�\3�F�Y������P�[�X������Ɖ����T���v����
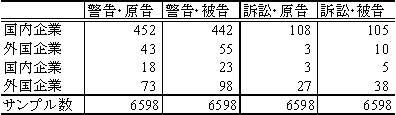
���̂悤�ɍ��ڂɂ���Ă͊Y���҂����������������݂��Ȃ����̂�����A���͂��s���ۂɂ͒��ӂ�v����B�����ł́A�����Ƃ̎�ʁi�������O���j�ɂ�����炸�A�@�x�����i�ׂ��A�A�����������O���������A�B�������퍐����8�ʂ�ɏW�v���ĕ��͂�i�߂邱�ƂƂ���B�܂��A���ꂼ��ɂ��ĊY������Ƃ�����Ɛ��̊�������ƋK�͕ʁA�ݗ��N�ʁA�Z�p����ʂɏW�v�������ʂ�\�S�Ɏ����B
(�\�S)
�܂��A�x���ɂ��ẮA���������Ō����̃P�[�X�ȊO�ɂ��ẮA��ƋK�͂��傫���Ȃ�قNJY����������������Ƃ����X����������B�܂���ƔN������Ȃ邱�Ƃɂ���ē��l�̌��ʂƂȂ��Ă���B�Z�p����ʂɌ���Ɓu�d�q�f�q�v�ɂ����Ă�⍂�������ƂȂ��Ă���A�u�r�W�l�X���@�v�ɂ����ĒႭ�Ȃ��Ă���Ȃǂ̌X����������B�u���i�v�ɂ��Ă͂���قǍ����l�ƂȂ��Ă��Ȃ��B
�܂��A�i�ׂɂ��Ă͌��������Ȃ����ߌX����ǂݎ�邱�Ƃ͓�����A�x���̏ꍇ�Ɠ��l�ɍ��������Ō����ƂȂ�P�[�X�ȊO�͋K�͂��ƔN��Ɛ��̑��֊W��������B�Z�p����ʂɂ́A�ۗ������X���͌����Ȃ��B
���̂悤�ɏW�v�\����͌X����ǂݎ�邱�Ƃ͍���ł��邱�Ƃ���A8�ʂ�̂��ꂼ��̃P�[�X�ɂ��ĕ����������v�������ϐ��Ƃ��A�ȉ��̕ϐ�������ϐ��Ƃ�����A���͂��s�����B�Ȃ��A���f����negative binominal���f���ł���B
�E
EMP�F��ƋK�́i�]�ƈ����̎��R�ΐ��j
�E
AGE�F��ƔN��i�N�̎��R�ΐ��j
�E
EMPAGE�FEMP��AGE�̌�����
�E
IPEMP:�m�I���Y����̏]�ƈ����̎��R�ΐ�
�E
PATSIZE�F�p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���i���L�����̎��R�ΐ��j
�E
TECHHT�F��Ƃ̏o������Z�p���ށi8���ށj�Ɋւ���n�[�t�B���_�[���w��
�E
��Ƃ̋Z�p���ނɊւ���_�~�[�ϐ��F�u�H�i�v���
���ʂɂ��Ă͕\�T�̂Ƃ���ł���B
(�\�T)
�@�܂��A��A���͂ɂ���Ė��炩�ɂȂ����_�Ƃ��ẮA�\�S�Ō���ꂽ��ƋK�͂Ɠ��������̑��֊W�͎�Ƀp�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���ɂ����̂ł��邱�Ƃ���������B���ЕۗL�������������قǓ��������̌�����퍐�ɂȂ�m�����������Ƃ͎��R�ł���B�p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫�����R���g���[������ƁA��ƋK�͂̑傫����Ƃ͓��������̔퍐�ɂȂ�m���������A����Ŋ�ƋK�͂̏�������ƂقǑi���鑤�ɂȂ邱�Ƃ������Ƃ������ʂ������ꂽ�B���̌X���͓��ɍ��������ɂ��Č����ł���B�܂��A��ƔN��͓��������Ƃ̊W�͌����Ȃ����ꕔ�Ŋ�ƋK�͂Ƃ̌������ɓ��v�I�L�ӂȌW����������B���������E�x���E�����̃P�[�X�ɂ��ẮA��ƔN������قNJ�ƋK�͂ƕ����̋t���֊W�����܂邱�ƁA���������E�x���E�퍐�̃P�[�X�ɂ��ẮA�t�Ɋ�ƔN��Ⴂ�قNJ�ƋK�͂ƕ����̐��̑��֊W�����܂邱�Ƃ������Ă���B
�@����̉�A���͂ɂ����ẮA�m������ɂ�����S���Ґ��iIPEMP�j�������ϐ��̂P�Ƃ��ĉ����Ă���BIPEMP�͕����ƊT�ː��̑��֊W�����邱�Ƃ��ώ@����邪�A����͓��������̑�����Ƃɂ����Ă͒m��������������Ă���Ƃ����t�̈��ʊW�ɂ����̂ł���\��������B�Ȃ��A�m�����傪�[�����Ă�����Ƃ́A������ƂƔ�ׂē��������ɂ�������͂������ƍl�����邱�Ƃ���A�퍐�Ƃ��Ă̓��������Ɋ������܂�ɂ����Ƃ����c�_�����݂��邪�iLanjouw and Schankerman, 2001�j�A�����ł͋t�̌��ʂƂȂ��Ă���B�܂��A�����J���̃t�H�[�J�X�x�iTECHHT�j�ɂ��ẮA�O�������Ɋւ��镴���i�����A�퍐�Ƃ��j�Ɛ��̑��֊W���ώ@�����B�O�߂Ō����悤�Ɍ����J���̃t�H�[�J�X��������Ƃɂ����ẮA���蕪��ɂ�����������x�������Ȃ�A���Y����ł̓��������Ɋ������܂�₷���Ƃ����\��������B���������̓_�ɂ��ẮA�n�[�t�B���_�[���w�����Z�o���邽�߂̋Z�p���ނ��\���ɍׂ����Ȃ�Ƌt�̌��ʂɂȂ邱�Ƃ��l�����A������ڍׂȕ��͂��K�v�ł���B�Ō�ɋZ�p����_�~�[�ɂ��ẮA�ۗ����������������Ȃ��Ƃ������ʂɏI������B
�@�č��ɂ����ẮA���������̌X�̃P�[�X�Ɋւ���f�[�^�x�[�X��p�����ڍׂȕ��͂��s���Ă���iLanjouw and Schankerman, 2001, 2003�j�B���̌��ʂɂ��Ă͈ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B
�E
��ƋK�͂��傫���Ȃ�ق�1����������̓��������̊m�����Ⴂ�B
�E
��Ƃ̃p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫���قǓ��������̊m�����Ⴂ�B���̌X���͊�ƋK�͂̏�������ƂقNj����B
�E
�p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑��ΓI�ȑ傫���i���p���������ۗL��Ƃ̑傫�����x�[�X�Ƃ����j���傫���Ȃ�ƕ����m�����Ⴍ�Ȃ�B
�E
���Y�����̋Z�p����ɂ�����W���x�i�����̊�Ƃɂ���ĕۗL����Ă���j�������قǕ����m�����Ⴍ�Ȃ�B
�E
�N���[�����̑傫�������قǕ����̊m���������B
�E
���p�����������iforward citation�j���傫�������͕����̊m���������B
�E
���p���Ă���������ibackward citation�j���傫�������͕����̊m�����Ⴂ�B
���̕��͌��ʂ͕����̑ΏۂƂȂ����X�̓����Ɋւ���f�[�^�x�[�X���瓱���ꂽ���̂ł���A�m��������p���čs������ƃ��x���̕��͂ƒ��ڔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���A�m�������ɂ����镴���̌��������ꂼ��P�̓����ɑ�����̂ł���Ɖ��肵�āA�����������e�Ђۗ̕L�������Ŋ��������̂��m���̑㗝�ϐ��Ƃ���Ɠ���ɕ��͂��\�ł���B�\�U�͂��̕����m���Ɋւ���㗝�ϐ���patsize�������\�T�̐����ϐ��ʼn�A���͂��s�������ʂł���B�Ȃ��A���f����OLS�ŁA���ꂼ��̓��������ɂ�����1���ȏ�̃P�[�X������T���v���݂̂�ΏۂƂ��Đ��v���Ă���B
(�\�U)
�@�܂��A��ƋK�͂ƕ����m���͕��̑��֊W�������ALanjouw and Schankerman�iL&S�j�̌��ʂƓ��l�̌��ʂ�������BL&S�́A���̊W���@trading�i��ƋK�͂��傫���ƃN���X���C�Z���X�Ȃǂœ�����trade���s���₷�����ߕ����ɂ�����m�����Ⴍ�Ȃ�j�y�чArepeated interactions�i�K�͂̑傫����ƂقǕ������N�������ݓI�ȑ���Ƃ̌𗬂����ڂł��蕴���ɂ�����m����������j�ɂ����̂Ƃ��Ă���B����̕��͂ł́A��ƔN������Ȃ�ƕ����m���̒ቺ�������Arepeated interactions�Ɋւ��鉼���Ɛ����I�Ȍ��ʂƂȂ��Ă���B�܂��Atrading�ɂ��Ă̓p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���������ϐ��Ƃ��Ďg�������߂����ł̓e�X�g�ł��Ȃ��������A��2�߂̕��͂ɂ�����p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫����Ƃ͎��Г����̑��Ў��{�ɂ������ăN���X���C�Z���X����葽���p���Ă���Ƃ������ʂƐ����I�ł���B
�@�p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑��ΓI�ȑ傫���Ɠ��������̊W�ɂ��ẮA�p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫����Ƃ̓��C�Z���V���O�̌��͂ɂ����ĕ����Ɏ���O�ɗL���Ȏ��{�����Ō_�������ł���ƍl������B�]���āA�����Ƃ��ē��������ɂ�����m�����������Ƃ������W�b�N�ł���B����̕��͂ł́A���������̑������肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���̉����ڃe�X�g���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����̏ꍇ�Ɣ퍐�̏ꍇ�Ŕ�Ώ̓I�ȉe�����l�����鉼���Ƃ��ċ����[���B�x���ɂ����Ċ�ƋK�͂Ƃ̕��̑��֊W���A�����̏ꍇ���v�I�L�ӂł���̂ɑ��āA�퍐�̏ꍇ�͗L�ӂł͂Ȃ��Ƃ������ʂ͂��̉������T�|�[�g���Ă���B�������A�i�ׂ̏ꍇ�͓��l�̌��ʂƂȂ��Ă��Ȃ��ƁA�����Ɣ퍐�̔�Ώ̐��ɂ��Ă͂��̑��̗l�X�ȗv�����l�����A���ڍׂȕ��͂�҂K�v������B�Ⴆ�A��2�߂̕��͌��ʂ���A���ЂŐ����A�̔��܂ł̌o�c������L���Ȃ�������Ƃ́A���ƂƔ�ׂĕۗL�����̑��Ў��{�����������Ƃ������Ƃ����������B���̂悤�Ȓ�����Ƃ͑��ƂƔ�ׂāA���Ђɑ��Čx�����邱�Ƃ��A�x������m����荂���Ȃ�ƍl���邱�Ƃ͎��R�ł���B
�@L&S�ł́A�����̎��i�N���[���̐���T�[�e�[�V�������j�������m���ɗ^����e���͂��Ă��邪�A����A���l�̕��͂��s�����Ƃ͓���B�������̈���ŁA��ƃ��x���̃f�[�^��p���邱�Ƃɂ����L&S�ł͍l������Ă��Ȃ��_�ɂ��ĕ��͂��邱�Ƃ��\�ł���B�P�͒m������̐l�����ɂ��Ăł��邪�A�x�����錏���Ɛ��̑��֊W������ꂽ�B���̈���Ŕ퍐�ɂȂ�ꍇ�͓��v�I�L�ӂł͂Ȃ����̂̌W���͕��ƂȂ��Ă���A�����̃��C�Z���V���O��ϋɉ������Ɛ헪�����������̌����ɉe����^���邱�Ƃ������Ă���B�܂��A��Ƃ̌����J���̃t�H�[�J�X�x���A���������̌����̏ꍇ���̑��֊W������A�퍐�̏ꍇ���̑��֊W�����邱�Ƃ������[���B�������A�\�T�Ŏ�������������������ϐ��Ƃ��镪�͌��ʂł́A�����̏ꍇ�����ƂȂ�ꍇ�������A���ڍׂȕ��͂�K�v�Ƃ��Ă���B
�@
�S�D���_
�{�_���ł́A�m�������̌[�f�[�^��p���āA�����̎��{����������ɌW����Ԃɂ��āA��ƋK�͂̈Ⴂ�Ƀt�H�[�J�X���Ȃ��番�͂��s�����B�����̎��ЕۗL�����̎��{�ɂ��ẮA��ƋK�͂���������ƔN��Ⴂ��Ƃ́A���Ў��{�������Ⴍ�A���Ў��{�������������Ƃ����������B�t�ɁA���Ђ̓����̎��Ђւ̎��{�ɂ��ẮA���ƂƔ�ׂĊ����ɍs���Ă��Ȃ��Ƃ������ʂɂȂ����B�o�c�����̖R����������Ƃ��A�����J���̐��ʂ����O�Ŏ��{���Ċ�Ɨ��v�ɂȂ��Ă������Ƃ�����ł��邽�߁A���Ђւ̃��C�Z���V���O�����������Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�������x�͂��̂悤�ȊO���Z�p�}�[�P�b�g���m��������̂Ƃ��āA���Ɍo�c�����ɖR����������ƂɂƂ��Ă͏d�v�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�܂��A�N���X���C�Z���X��L�����{�Ȃǂ̎��{�̌`�Ԃɂ��ẮA�]�ƈ����Ō�����ʓI�Ȋ�ƋK�͂��ƔN��̉e���͏������Ȃ�A�ۗL�������i�p�e���g�|�[�g�t�H���I�j�̑傫�����d�v�̓t�@�N�^�[�Ƃ��Č���邱�Ƃ����������B�Ⴆ�N���X���C�Z���X���g�������̓p�e���g�|�[�g�t�H���I�̑傫���Ɛ��̑��֊W������B���͌��ʂ���͋K�͂̏�������Ƃł��傫�ȃp�e���g�|�[�g�t�H���I�����ĂΑ��ƂƂ̃N���X���C�Z���X���\�ł���Ƃ������Ƃ��ł��邪�A�N���X���C�Z���X�͂��݂��ɓ��������{����ꍇ�ɐ�������̂ŁA��͂莩�Ђɂ����Đ�����̔��ȂǕ���������Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B�]���āA�����J���^�̒�����ƂɂƂ��ẮA�L���ł̃��C�Z���X����������ɍs�����������Ă��邩�ǂ������d�v�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�����Ń��C�Z���V���O�̌��ɂ����Ē�����Ƃ��s���ȗ���ɗ�������Ă��Ȃ����Ƃ����_�ɂ��Ă̌����K�v�ɂȂ��Ă��邪�A��3�͂ł͓������Ɋւ���x����i�ׂɊւ���f�[�^��p�������͂��s�����B�����̌����������ϐ��Ƃ��郂�f���ł́A��ƋK�͂�p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫����ƂقǁA�x����i�����������Ƃ������ʂɂȂ����B�����̑ΏۂƂȂ肤��p�e���g�|�[�g�t�H���I���傫���ƁA����������������͎̂��R�̋A���ł���B�]���āA�lj��I�ȕ��͂Ƃ��āA������������Ƃ̓������L�����Ŋ���������1��������̕����m���������ϐ��Ƃ��郂�f���𐄌v�����B���̌��ʁA��ƋK�͂��������A��ƔN��̎Ⴂ��ƂقǕ����m���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������B���������{�Ɋւ��镪�͌��ʂɌ����悤�ɁA������Ƃ͓����̑��Ђւ̃����Z���V���O��ϋɓI�ɍs���Ă����K�v������B�]���āA���������Ɋ������܂��m���͎����ƍ��܂�Ƃ������Ƃ��l������B�܂��A����̕��͌��ʂł́A�����̎��ɂ��ẴR���g���[���͍s���Ă��Ȃ��Ƃ����������݂���B�������Ȃ���A���̌��ʂ́AL&S�ł��w�E����Ă���悤�ɒ�����Ƃ����C�Z���X���ɂ����Ďア����ɂ���\�����������Ă���_�ŏd�v�ł���B
���̓_�ɂ��ẮAL&S�ł��s���Ă���悤�ɓ��������̃P�[�X�����ڍׂɕ��͂��Ă������Ƃ��K�v�ł���B�܂��A���C�Z���V���O�̌��ɂ����Ē�����Ƃ��s���ȗ���ɗ�������Ă���Ƃ���ƁA������Ƃ͂����D�荞��Ō����J�����s���Ă��邱�Ƃ��l������B������Ƃ́A���������������₷���Z�p�̈������Č����J�����s���Ă���Ƃ����������ʂ����݂���iLerner, 1995�j�B�C�m�x�[�V�����̃v���Z�X�ɂ����āA�����Z�p�̑g�ݍ��킹���d�v�ƂȂ�complexity�������Z�p�̈�ɂ��ẮA������Ƃ̑��ΓI�ȃo�[�Q�j���O�|�W�V�����̒ቺ����茰�݉����邱�Ƃ��l������B�Z�p�̈�ʂ̏ڍׂ͕��͂��s�����Ƃɂ���Č����J���헪�ƃ����Z���V���O�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��Ă����K�v������B
�Ō�ɁA����̃��T�[�`�v���W�F�N�g�́A�m�������̌[��p�����p�C���b�g�X�^�f�B�Ƃ����ʒu�Â��ƂȂ��Ă���̂ŁA����A�m���������s���ɂ������ĉ��P���ׂ��_�ɂ��ďq�ׂ����B��Ɗ�����{�����ȂǁA���Ɋ�Ƃ̒m�I���Y�����Ɋւ��钲���͑��݂��邪�A�m�������͊����̒����Ɣ�r���Ċi�i�ɏڍׂȏ�����A���͂��s����ł̔��ɗL�Ӌ`�ȓ��v�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�������A�ڍׂȒ������s�����Ƃ́A���̈���ʼn������f�[�^���x�˂�댯�������邱�Ƃ�F�����邱�Ƃ��d�v�ł���B
����A���͂Ɋ��p�����Z�N�V�����ɂ����āA���ɒm�I���Y���N�Q�Ɋւ��鍀�ڂ͉ߓx�ɏڍׂł���\��������B�������Ɋւ���f�[�^������Ɓi�\3�j�A���ڂ��ڍׂ����邽�ߊY����ƌ������ɒ[�ɏ������Ȃ��Ă���B�\3�ł́A���f�[�^�ɂ����đΊO����Ƃ��S�̒n��ʂɕ�������Ă�����̂��P�ɂ܂Ƃ߂����A����ł��Y�������������Ƃ������ڂ����݂���B�g�����h�ɂ��ẮA�W�v���ꂽ���݂̂̂Ƃ��āA���̑��̏ڍׂȏ��͐��N�����܂Ƃ߂Ď����I�ɒ�������Ƃ��̍H�v���K�v���ƍl����B�܂��A���l�̂��Ƃ͓����̏o����тƌ����݂̋Z�p���ނɂ��Ă�������B�Ⴆ�Ίe�N�̃g�����h�͏W�v���ꂽ���݂̂̂ɂ��āA�Z�p���ނ́A2004�N�܂�3�N�Ԃ̍��v���L�����Ă��炤�Ȃǂ̍H�v���K�v�ł���ƍl����B
�Q�ƕ���
�����@��V(2003)�u�Y�w�A�g�̎��Ԃƌ��ʂɊւ���v�ʕ��́F���{�̃C�m�x�[�V�����V�X�e�����v�ɑ���C���v���P�[�V�����v�ARIETI�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[03-J-015�A2003/11�A�o�ώY�ƌ�����
Audretsch,
D. (1999), Small Firms and Efficiency, in Are Small Firms Important?: Their Role and Impact, Z. J. Acs ed, Kluwer Academic Pub
Arora A., A. Fosturi and A.
Gambardella (2001), Markets for
Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy, MIT Press
Hall B. and R. Ziedonis
(2001), An Empirical Study of Patenting in the US Semiconductor Industry,
1979-1995, Rand Journal of Economcs,
Vol. 32, No. 1 pp. 101-128
Lanjouw, J. O. and M.
Schankerman (2003), Enforcement of Patent Rights in the
Lanjouw, J. O. and Mark Schankerman (2001)
�gCharacteristics of Patent Litigation: A Window on Competition,�h The Rand Journal of Economics. Vol. 32,
no. 1, pp. 129-51.
Lerner, J. (1995),Patenting in
the Shadow of Competitors, Journal of Law and Economics, vol. 38, pp. 463-96